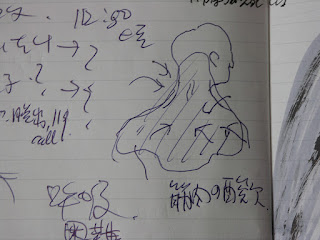2017年7月29日土曜日
2017年7月15日土曜日
vol.016 #161103 絵巻運河日記
fb 橋本 公成: 2016年11月3日
いろんなプロジェクトが同時進行し、アート「プロジェクト」というより「日常」になってきているような中川運河リミコライン・アートプロジェクト。今週末もいくつかのイベントが並行して行われるようです。楽しそうです。皆さん是非に。
一昨年より、たびたび散歩した中川運河周辺。先々月行ったミャンマーでも運河や川のことが気になって仕方ありません。僕の中でも運河について思いをめぐらせることが日常のようになっているようです。今週末、僕は、未来に起こらなかったことを思い出して、長い夏休みの宿題のような絵日記を持って行きます。それは芸術なの?
vol.019 # making of OOBORAFUKI
ボラの研究と制作
設計から一週間弱、とりあえず中川運河での進水試験にこぎつける。
コバルトが少量だったため硬化時間がかかってしまい焦ったが。。
 |
170522/ 21:20
|
 |
170522/ 22:18
|
 |
170523/21:12
|
 |
170525
|
 |
170525/ 04:33
|
 |
170525/ 05:32
|
 |
170525/05:33
|
 |
170525/ 21:12
|
 |
170525/22:51
|
 |
170526/01:10
|
 |
170526/ 08:29
|
 |
170526/ 08:31
|
 |
170526/ 09:06
|
 |
170526/ 22:41
|
 |
170517/ 02:43
|
 |
170527/ 03:14
|
 |
170527/ 04:06 temporary watering test
|
設計から一週間弱、とりあえず中川運河での進水試験にこぎつける。
コバルトが少量だったため硬化時間がかかってしまい焦ったが。。
vol.010 # コード
視覚情報中心の美術展覧会場で、テキストを読む行為というのはよっぽどのつかみがない限り難しいことだ。
文人たちはコードを読み込むことに腐心していた。
コードを読み込み、場に落とし込んでゆく。
この工程は近年の街づくり再開発アート事業にとっては、あたりまえの、まじめな取り組みを示す行為であったし、なにより周りのもともとそこに住んでいる人たちにとっての説得力も持ち合わせているように見えるアカデミックな風景だった。
いくつかのキーワード、いくつかの忘れられていたその場の由来やエピソード、伝統技術そして発祥。
それらは、この場所がどこでもないここであることを雄弁に示しているように思われた。
場を消費しないとは。
文人たちはコードを読み込むことに腐心していた。
コードを読み込み、場に落とし込んでゆく。
この工程は近年の街づくり再開発アート事業にとっては、あたりまえの、まじめな取り組みを示す行為であったし、なにより周りのもともとそこに住んでいる人たちにとっての説得力も持ち合わせているように見えるアカデミックな風景だった。
いくつかのキーワード、いくつかの忘れられていたその場の由来やエピソード、伝統技術そして発祥。
それらは、この場所がどこでもないここであることを雄弁に示しているように思われた。
場を消費しないとは。
vol.107 #とどのつまり
とどのつまり ~鯔の話~
皐月のある日、毎年その日は突然にやってくる。
真夏のような暑さが始めてきた日。
春一番ならぬ夏一番と言ってよい日。
羽蟻が湧くように大量に飛び立つ日。
ベランダの屋根を支える木の柱の根元、木造の風呂場の腐った木の柱には注意である。しかし、なぜに、その日なのか?
八朔の頃のある日、背丈ぐらいの木から玉虫が大量に湧いた。
一匹、二匹と言ったものではない。湧くというにふさわしいほどの大量だ。
子供の頃、見つけることができなかった珍しいな玉虫。
今、ここで、大量に発生している。
それは成虫になったばかりの誕生の日だろうか。
それとも荘厳な種の保存のための性交の日だろうか。
なぜに、その背丈ほどしかない若い木に集まるのか。
あの木は何の木だったか?
虫は、その日がわかるのだろうか。
其処を通るたびに思い出し、あの時の謎がよみがえるが、宅地に造成され跡形もなくなった今となっては祇園祭りである。
水無月のある日、運河に大量の鯔が浮いた。
鰡さんの話
箱根に足を伸ばして登山鉄道の小涌谷で降りる。目指すは光琳の鴨の屏風がある美術館だが、かなり距離があるようだ。なによりも山である。天下の剣、箱根である。
三拾度の坂をぜえぜえしながら、
「小一の頃は、羽曳野病院バス停に向かう急な坂道を毎日歩いていたのに、まったく、こんな坂道も登れなくなっちまったか。情けねえ。。」
息苦しく、途中で鴨の屏風は断念する。
その山行きから戻った夜にその異変は起きた。肩全体から背中にかけて、巨人に掴まれ押し付けられてるような圧迫感。
「日ごろからの運動不足がたたったのじゃ」
自分の中の天の声がつぶやく。
しかし不思議だ。運動すればするほど肩がこるような背中全体が固まったような圧迫感。有酸素運動と肩こりの不思議な関連。母がしょっちゅうこぼしていた、肩が詰まるという感覚はこのことか。
さっそく風呂に火を入れ、沸く前に、ここは荒療治と、腕立て伏せを二十回、一気に試みる。
するとどうだ、背中の圧迫感は解消するどころか、さらに硬直し、今まで経験したことがない呼吸困難に襲われた。まだ寒い夜中に窓を開け放ってはぁーはぁーと深呼吸を試みる。
トドのつまり、かつて経験したことのない出来事は不可逆的に起こる。
経験したことのない痛み、圧迫感、それはすでに十年前のその年に起こっていたのである。
初見の見立て違いによって対応はまったく異なった方へ向く。
夜勤、研修医の夜中の救急外来では総合医療的な判断は行われない。
「医療判断ミス」そんなことを言っても仕方ない。現代は分業化されたスペシャリストの時代でジェネラリストの知見は軽視されるというよりそういったシステムが構築されにくい世なのだ。
すでに十年前の不可逆的な病だ。つまり、身から出たさび、自の身は自分で守らなければならないという当たり前のことを目の前に突きつけられたのだ。
十年前の発作。その年だけに三回から四回起こっただろう発作。徹夜明け、麦酒をジョッキで二杯飲んだ後に、その息苦しさに襲われた。
ピーポーは迷わずに心臓外科へむかう。
「心筋梗塞の発作とはこのようなものか?」その時は、そう考えたのだが、夜勤のドクターがあらゆる心臓の検査を行い、「異常なし」を連発するその時も、喉の下あたり、明らかに心臓の位置からずれている、正中線にあるその箇所は苦しさを訴えていたのだった。
「あとは一泊してカテーテル検査しかないですね。どうします?」そんな言葉を聴いているうちに、息苦しさは薄らいでいった。
翌日になると、その時の感覚を忘れてしまった。
しかし五拾前、何か異変が起こってもおかしくない年齢と、数日後、改めて同じ大きな病院へ行く。偶然にもあの時の救急外来で対応してくれたドクターだ。
その日の通り一遍の検査結果にドクターは
「鰡さん、心臓は、まったく丈夫いですよ」
そんなお墨付きをもらって喜んでいる場合ではない。それではピーポーまで呼んだあの発作はなんだったのか。
蒸し暑いという感覚が今年もやってきた水無月のある日、におひだした運河に大量の鯔が浮いた。
鰡さんはその夜、肺の中で酸欠になって苦しく飛び跳ね、そして溺れていった鯔の夢を見た。
トドのつまり、かつて経験したことのない出来事は不可逆的に起こる。
ボラは出世魚である。関東ではオボコ→イナッコ→スバシリ→イナ→ボラ→トド、関西ではハク→オボコ→スバシリ→イナ→ボラ→トド。
子供の幼い様子を表す「おぼこい」の語源になったオボコは未通女と書いてオボコと読み処女を意味す。若い衆の月代の青々とした剃り跡を、青灰色でざらついた背中に見立て「いなせ」の語源になったイナ。
そして、さかなへんに老いと書く、成長しきったオオボラ、トド。これ以上大きくならない、行き着くところまで行き着いた「結局」。「とどのつまり」の語源である。
皐月のある日、毎年その日は突然にやってくる。
真夏のような暑さが始めてきた日。
春一番ならぬ夏一番と言ってよい日。
羽蟻が湧くように大量に飛び立つ日。
ベランダの屋根を支える木の柱の根元、木造の風呂場の腐った木の柱には注意である。しかし、なぜに、その日なのか?
八朔の頃のある日、背丈ぐらいの木から玉虫が大量に湧いた。
一匹、二匹と言ったものではない。湧くというにふさわしいほどの大量だ。
子供の頃、見つけることができなかった珍しいな玉虫。
今、ここで、大量に発生している。
 |
| 0803-2003: 一本の木にタマムシが3-40匹群がっていた日、蝉も大量に羽化したようだ。 |
それは成虫になったばかりの誕生の日だろうか。
それとも荘厳な種の保存のための性交の日だろうか。
なぜに、その背丈ほどしかない若い木に集まるのか。
あの木は何の木だったか?
虫は、その日がわかるのだろうか。
其処を通るたびに思い出し、あの時の謎がよみがえるが、宅地に造成され跡形もなくなった今となっては祇園祭りである。
水無月のある日、運河に大量の鯔が浮いた。
鰡さんの話
箱根に足を伸ばして登山鉄道の小涌谷で降りる。目指すは光琳の鴨の屏風がある美術館だが、かなり距離があるようだ。なによりも山である。天下の剣、箱根である。
三拾度の坂をぜえぜえしながら、
「小一の頃は、羽曳野病院バス停に向かう急な坂道を毎日歩いていたのに、まったく、こんな坂道も登れなくなっちまったか。情けねえ。。」
息苦しく、途中で鴨の屏風は断念する。
その山行きから戻った夜にその異変は起きた。肩全体から背中にかけて、巨人に掴まれ押し付けられてるような圧迫感。
「日ごろからの運動不足がたたったのじゃ」
自分の中の天の声がつぶやく。
しかし不思議だ。運動すればするほど肩がこるような背中全体が固まったような圧迫感。有酸素運動と肩こりの不思議な関連。母がしょっちゅうこぼしていた、肩が詰まるという感覚はこのことか。
さっそく風呂に火を入れ、沸く前に、ここは荒療治と、腕立て伏せを二十回、一気に試みる。
するとどうだ、背中の圧迫感は解消するどころか、さらに硬直し、今まで経験したことがない呼吸困難に襲われた。まだ寒い夜中に窓を開け放ってはぁーはぁーと深呼吸を試みる。
トドのつまり、かつて経験したことのない出来事は不可逆的に起こる。
経験したことのない痛み、圧迫感、それはすでに十年前のその年に起こっていたのである。
初見の見立て違いによって対応はまったく異なった方へ向く。
夜勤、研修医の夜中の救急外来では総合医療的な判断は行われない。
「医療判断ミス」そんなことを言っても仕方ない。現代は分業化されたスペシャリストの時代でジェネラリストの知見は軽視されるというよりそういったシステムが構築されにくい世なのだ。
すでに十年前の不可逆的な病だ。つまり、身から出たさび、自の身は自分で守らなければならないという当たり前のことを目の前に突きつけられたのだ。
十年前の発作。その年だけに三回から四回起こっただろう発作。徹夜明け、麦酒をジョッキで二杯飲んだ後に、その息苦しさに襲われた。
ピーポーは迷わずに心臓外科へむかう。
「心筋梗塞の発作とはこのようなものか?」その時は、そう考えたのだが、夜勤のドクターがあらゆる心臓の検査を行い、「異常なし」を連発するその時も、喉の下あたり、明らかに心臓の位置からずれている、正中線にあるその箇所は苦しさを訴えていたのだった。
「あとは一泊してカテーテル検査しかないですね。どうします?」そんな言葉を聴いているうちに、息苦しさは薄らいでいった。
翌日になると、その時の感覚を忘れてしまった。
しかし五拾前、何か異変が起こってもおかしくない年齢と、数日後、改めて同じ大きな病院へ行く。偶然にもあの時の救急外来で対応してくれたドクターだ。
その日の通り一遍の検査結果にドクターは
「鰡さん、心臓は、まったく丈夫いですよ」
そんなお墨付きをもらって喜んでいる場合ではない。それではピーポーまで呼んだあの発作はなんだったのか。
蒸し暑いという感覚が今年もやってきた水無月のある日、におひだした運河に大量の鯔が浮いた。
鰡さんはその夜、肺の中で酸欠になって苦しく飛び跳ね、そして溺れていった鯔の夢を見た。
トドのつまり、かつて経験したことのない出来事は不可逆的に起こる。
ボラは出世魚である。関東ではオボコ→イナッコ→スバシリ→イナ→ボラ→トド、関西ではハク→オボコ→スバシリ→イナ→ボラ→トド。
子供の幼い様子を表す「おぼこい」の語源になったオボコは未通女と書いてオボコと読み処女を意味す。若い衆の月代の青々とした剃り跡を、青灰色でざらついた背中に見立て「いなせ」の語源になったイナ。
そして、さかなへんに老いと書く、成長しきったオオボラ、トド。これ以上大きくならない、行き着くところまで行き着いた「結局」。「とどのつまり」の語源である。
登録:
コメント (Atom)